運転中にイヤホンを使っても本当に大丈夫?
片耳ならセーフ、骨伝導ならOKという話も聞くけれど、実際の法律やルールはどうなっているのでしょうか。
この記事では、「車の運転中にイヤホンを使うのは違法なのか?」という疑問を出発点に、道路交通法の規定や都道府県ごとの違い、警察に止められたときの対応、イヤホンの安全な使い方まで徹底解説。
さらに、運転中にも使いやすいおすすめイヤホン10選も紹介します。安全運転と快適なドライブを両立したい方は必見です。
目次
- 運転中にイヤホンを使うのは違法なの?
- 警察に止められたらどうなるの?
- 運転中にイヤホンを使うメリットとデメリット
- 片耳イヤホンはOK?両耳はNG?
- ずっとイヤホンをつけっぱなしでも大丈夫?
- 運転中におすすめのイヤホンタイプとは?
- 運転中でも使いやすいイヤホン10選
- 1. Shokz OpenRun(骨伝導イヤホン)
- 2. Shokz OpenComm(骨伝導・マイク付き)
- 3.JVCケンウッド KENWOOD KH-M500-B(片耳Bluetoothイヤホン)
- 4. Anker Soundcore V20i
- 5. AfterShokz OpenMove(骨伝導イヤホン)
- 6. Plantronics Voyager 5200(片耳Bluetoothイヤホン)
- 7. Shokz OpenFit2(オープンイヤー型イヤホン)
- 8. JVC HA-BD10BT(骨伝導イヤホン)
- 9.Nakamichi ナカミチサウンド
- 10. BONX Grip(チーム通話対応オープンイヤー型)
- 運転時の安全な通話・音楽の楽しみ方
- 知っておきたい!運転中の音響機器使用マナー
- まとめ:イヤホンを安全に使って快適なドライブを
運転中にイヤホンを使うのは違法なの?
車を運転しながらイヤホンを使うと、違反になることがあると聞いたことがあるかもしれません。では実際に、どのような基準で違法と判断されるのでしょうか?ここでは、まず法律での位置づけについて解説します。
道路交通法でのルールはどうなっている?

道路交通法 第70条(安全運転の義務)
「車両等の運転者は、当該車両等を安全に運転しなければならない。」
つまり、「周囲の音が聞こえなくなって運転に支障が出る状態」は違反とみなされるのです。
例えば、以下のような状況が該当します
-
両耳イヤホンで救急車のサイレンに気づかなかった
-
音楽に集中して信号を見落とした
-
通話に夢中でブレーキが遅れた
このようなケースでは、「安全運転義務違反」として取り締まりの対象になります。
ただし、すべてのイヤホン使用が即違法というわけではありません。
たとえば、「骨伝導イヤホン」や「片耳イヤホン」などで、外の音が聞こえる状態を保てるなら、使用が許容されることもあります。
✅ポイントまとめ:
イヤホンの使用自体が違法とは限らない
「外の音が聞こえない状態」が危険と判断される
条文は曖昧なので、使用者の判断と配慮が求められる
都道府県ごとに違うって本当?

はい、本当です。
実は、運転中のイヤホン使用に関しては道路交通法のほかに、各都道府県が定める「道路交通規則」によってルールが異なります。
下の表をご覧ください:
| 都道府県 | イヤホン使用の扱い(例) | 備考 |
|---|---|---|
| 東京都 | 周囲の音が聞こえない場合は違反 | 両耳イヤホンはほぼNG |
| 大阪府 | 注意力が妨げられると判断されれば違反 | 使用状況によって判断される |
| 愛知県 | 音が外部に聞こえない装置の使用は禁止 | 骨伝導や片耳タイプは比較的寛容 |
| 福岡県 | 周囲の音が聞こえることが条件 | 両耳・大音量はNG |
これらは一部の例に過ぎませんが、どの都道府県も共通して「外部の音が聞こえない状態」を危険とみなしています。
例えば、旅行先でいつものようにイヤホンを使っていたら、その地域ではNGだったということもあり得ます。
そのため、自分が運転する地域のルールを事前に確認することがとても大切です。
✅チェックポイント
「片耳」や「骨伝導」ならOKの地域も多い
使い方によっては同じイヤホンでも違反になる可能性あり
警察官の判断によって現場で注意や指導されることもある
結論:都道府県によって判断基準に違いがあるため、「どこでも同じ」と思わないことが重要です。
違反したらどんな罰則があるの?

運転中にイヤホンを使用し、「安全運転義務違反」として扱われた場合には、次のような罰則が科されることがあります。
| 違反内容 | 罰則内容 | 適用の可能性 |
|---|---|---|
| 安全運転義務違反 | 反則金(6,000円〜9,000円) 違反点数:1点〜2点 |
周囲の音が聞こえない・運転操作に支障がある場合 |
| 通信機器等の使用による違反(通話中) | 反則金(最大18,000円) 違反点数:3点〜6点 |
走行中の通話が原因で事故を起こした場合など |
| 事故を引き起こした場合 | 過失運転致傷・罰金・免許停止など | 状況により刑事罰や民事賠償も発生 |
📌補足ポイント

-
反則金は車種や違反の内容によって変わります。
例:普通車での「安全運転義務違反」は6,000円。 -
違反点数が加算されると、累積により免許停止の対象にもなります。
-
事故を起こした場合は、イヤホンの使用が「過失」と判断されることもあります。
たとえば、サイレンを聞き逃して救急車に道を譲らなかった場合など。
✅注意点
・「音楽を聴いていただけ」と思っていても、運転の注意がそれていれば違反になる可能性があります。
・「イヤホン=すぐ罰金」ではなくても、警察官が危険と判断すればアウトです。
警察に止められたらどうなるの?
運転中にイヤホンを使っていて、もし警察に止められたらどうすればよいのでしょうか?この章では、警察がチェックしているポイントや、止められたときの正しい対応方法について、順番にわかりやすく解説していきます。
警察の取り締まりのポイントとは

警察官が運転中のイヤホン使用を取り締まるとき、次のようなポイントをチェックしています。
-
両耳をふさいでいるか(両耳イヤホンは特に厳しく見られる)
-
運転に集中できていない様子があるか(ふらつき、ブレーキが遅いなど)
-
外の音が聞こえにくい状況か(クラクションに気づかないなど)
特に、両耳をイヤホンでふさいでいる場合はかなり注意されやすいです。
片耳だけならOKの県もありますが、それでも「音が大きすぎる」「周りの音が聞こえていない」と判断されれば違反とみなされることも。
また、警察は単に「イヤホンをつけていたか」だけでなく、その運転が危険だったかどうかを見ています。
安全運転義務違反に該当すると判断された場合、反則金や違反点数が科される可能性があります。
✅まとめ
-
両耳イヤホン=違反の可能性大
-
運転操作が不安定だと止められやすい
-
周囲の音が聞こえていないとNG
イヤホンしていて止められたらどう対応する?
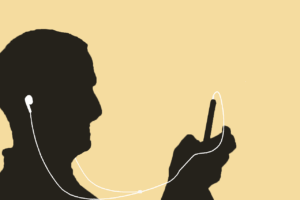
もし警察に止められてしまったら、次のように対応しましょう。
-
イヤホンをすぐに外す
-
エンジンを止める(安全な場所で)
-
警察官の指示に従い、落ち着いて受け答えする
止められたからといって、慌てたり、逆ギレしたりしてはいけません。
イヤホンの使用について聞かれたら、素直に答えましょう。
無理に言い訳をしようとすると、警察官の心証が悪くなり、かえって不利になることもあります。
また、運転に支障がなかったと自分では思っていても、警察の判断では「危険運転」とされることも。
あくまでも相手(警察)がどう判断するかが大事なので、争わないようにするのがポイントです。
✅ポイント
-
イヤホンはすぐ外す
-
無理な言い訳をしない
-
落ち着いて行動する
素直な対応が一番大切な理由

警察に止められたとき、素直に対応することがなぜ大切なのか?
それにはいくつかの理由があります。
-
違反でも注意だけで済むことがある
(素直に認めれば警告で終わる場合もある) -
警察官の心証が良くなる
(冷静で礼儀正しい態度はプラス評価) -
後の処理がスムーズになる
(必要以上にトラブルにならない)
たとえば、「イヤホンをしていた理由」を聞かれたとき、
「すみません、片耳で使っていましたが注意が足りませんでした」と素直に話せば、厳重注意だけで済むケースもあります。
逆に、「別に違反じゃないでしょ!」と反論すると、警察官も厳しく対応せざるを得なくなり、正式な違反切符を切られる可能性が高まります。
✅まとめ
-
反省の態度を見せることが大切
-
争わず、冷静に対応する
-
小さな違反でも処分が軽くなることがある
運転中にイヤホンを使うメリットとデメリット
運転中にイヤホンを使うことには、便利な面もあれば危険な面もあります。この章では、メリット・デメリットを両方しっかり整理して、使い方を考えるヒントを紹介します。
ハンズフリー通話ができる便利さ

運転中にイヤホンを使う大きなメリットは、ハンズフリー通話ができることです。
スマホを手に持って通話するのは完全に違反ですが、イヤホンなら手を使わずに会話できます。
【ハンズフリー通話のメリット例】
-
重要な電話にすぐ応答できる
-
手をハンドルから離さず安全に話せる
-
運転中に道案内やナビアプリの指示を聞ける
たとえば、仕事中に取引先からの緊急連絡を受けたり、家族と待ち合わせの相談をしたりするとき、
イヤホン+マイク付きならスムーズに対応できます。
ただし、イヤホンを使っていても「通話に夢中になりすぎて運転がおろそか」になったら本末転倒。
あくまで運転に集中することが最優先です。
✅まとめ
-
スマホを持たずに通話できるのは大きなメリット
-
使い方次第では安全性も高まる
-
通話に気を取られすぎないよう注意!
耳がふさがって事故のリスクが上がる?

運転中にイヤホンを両耳に装着すると、周囲の音がほとんど聞こえなくなり、事故のリスクが大きく高まります。
【両耳イヤホンによるリスク】
-
クラクションやサイレンに気づかない
-
周囲の車両やバイクの接近に気づけない
-
歩行者や自転車に対する注意が遅れる
たとえば、交差点で救急車が近づいてきても音に気づかなければ、道を譲ることができません。
また、後方からバイクが追い越そうとしているのに、まったく気づかずに進路変更してしまう事故も起こっています。
両耳を完全にふさぐのは、たとえ小音量でも危険です。
音楽や通話に集中しすぎると、視界だけでは気づけない危険を見落としやすくなります。
✅まとめ
-
両耳をふさぐと周囲の音が聞こえず非常に危険
-
事故のリスクが大幅に上がる
-
基本的に運転中は「片耳使用」または「外音が聞こえるタイプ」を選ぼう
周囲の音が聞こえにくいことの危険性

運転中に最も頼りにしている情報源は「目」ですが、耳もとても重要なセンサーです。
耳から入る情報が減ると、危険に気づくタイミングが遅れてしまいます。
【耳が大事な理由】
-
サイレンやクラクションなど緊急の音が聞こえる
-
バイクや自転車の近づく音を察知できる
-
後ろの車が接近しているかを耳で感じ取れる
たとえば、後方からクラクションを鳴らしている車があった場合、耳で聞こえればすぐに気づいて進路変更などを控える判断ができます。
しかし、イヤホンで音を遮断していたら、気づかないままトラブルになってしまうかもしれません。
特に、夜間や悪天候など視界が悪い状況では、耳からの情報が命を守る鍵にもなります。
✅まとめ
-
音からの情報は安全運転に欠かせない
-
音が聞こえないと危険に反応できなくなる
-
運転中のイヤホン使用は「音が聞こえるか」が大きな判断基準
片耳イヤホンはOK?両耳はNG?
「運転中にイヤホンを使っても、片耳なら大丈夫」と聞いたことがある人も多いはず。でも本当に安全なのでしょうか?
ここでは、片耳と両耳の使い方の違いや、それぞれに潜むリスクについて詳しく解説していきます。
片耳ならセーフな都道府県が多い

結論から言うと、片耳だけイヤホンをつけることは、多くの都道府県で許容されています。
なぜなら、片耳が空いていれば、周囲の音(クラクションやサイレン)が聞こえやすいためです。
【片耳イヤホンがOKとされる理由】
-
一方の耳で外の音をキャッチできる
-
両耳ふさぐよりも運転への影響が少ない
-
緊急時にすぐ対応できる
たとえば、東京都や大阪府では「周囲の音を聞き取れる状態であれば可」とされています。
ただし、どれだけ小さな音量でも、運転に集中できないと警察に判断された場合は、片耳でも違反となる可能性があるので注意が必要です。
✅ポイント
-
片耳イヤホンでも「安全第一」で使用すること
-
音量は小さく、周囲の音がしっかり聞こえる状態を保とう
-
両耳使用と間違えられないよう、見た目にも配慮を
両耳使用は原則NGの理由

両耳にイヤホンをつけるのは、原則としてほぼすべての都道府県で禁止と考えた方がいいでしょう。
理由はとてもシンプルです。両耳をふさぐと、周囲の音がほぼ聞こえなくなるからです。
【両耳イヤホン使用の主な問題点】
-
救急車のサイレンに気づかない
-
クラクションや警察車両の接近音が聞こえない
-
周囲の状況判断が大幅に遅れる
たとえば、信号待ちをしている間に、緊急車両が後ろから来たとしても、両耳イヤホンでは気づけず道を譲れないケースが考えられます。
また、両耳イヤホンで音楽を聞いていると、無意識にリズムを取ってしまったり、注意力が散漫になることも大きなリスクです。
✅ポイント
-
両耳をふさぐと「周囲の音情報ゼロ」に近くなる
-
事故リスクが急激に上がる
-
ルール以前に、自分と周りの人の安全を守る意識が大切
法的なグレーゾーンとそのリスク

運転中のイヤホン使用に関しては、法律が完全に明文化されていない部分もあります。
これが「グレーゾーン」と呼ばれる理由です。
【なぜグレーゾーンなのか?】
-
道路交通法ではイヤホン自体を禁止していない
-
「運転に支障をきたす場合は禁止」と表現が曖昧
-
最終的な判断は現場の警察官に委ねられる
つまり、イヤホンをしているだけでは違反にはならないかもしれませんが、
・音量が大きすぎる
・外の音が聞こえない
・運転操作が雑になっている
これらが見られた場合、即座に違反とされる可能性があります。
さらに、事故を起こしたときには「イヤホンしていた=過失」とみなされ、重い責任を問われることも。
たとえば、歩行者との接触事故を起こした場合、イヤホン使用の事実だけで過失割合が大きくなることもあります。
✅まとめ
-
グレーゾーンだからといって油断は禁物
-
最悪の場合、刑事責任や民事責任が重くなる
-
安全のためには「使わない」または「片耳+小音量」を基本にしよう
ずっとイヤホンをつけっぱなしでも大丈夫?
運転中だけでなく、長時間イヤホンをつけっぱなしにしている人も多いですよね。でも、イヤホンの長時間使用には意外なリスクが潜んでいます。この章では、耳への影響や正しい使い方について解説します。
長時間使用による耳への影響

イヤホンを長時間使い続けると、耳にさまざまな負担がかかります。
特に運転中は気づかないうちに何時間もつけっぱなしになってしまうこともあります。
【長時間イヤホン使用による主な影響】
-
耳の中が蒸れて雑菌が繁殖しやすくなる
-
耳の奥の皮膚が炎症を起こす(外耳炎)
-
音を聞く細胞(有毛細胞)が疲れる
たとえば、片道2時間のドライブでイヤホンをつけっぱなしにしていると、耳の中が高温・高湿度になり、雑菌が繁殖しやすい環境になります。これが原因で耳がかゆくなったり、痛みを感じたりすることもあります。
✅まとめ
-
イヤホンの長時間使用は耳への負担大
-
衛生面でも悪影響が出る可能性あり
-
運転中もこまめに外して耳を休ませよう
耳鳴りや難聴のリスクもある

さらに怖いのは、イヤホンの使いすぎが「耳鳴り」や「難聴」を引き起こすリスクがあるということです。
【イヤホンによる耳障害リスク】
-
長時間高音量で音を聞くと聴覚神経がダメージを受ける
-
有毛細胞が壊れると回復しない
-
若くても「音響性難聴」になるケースが増加
たとえば、音量を60%以上に設定し続けると、わずか1時間でも聴覚に悪影響が出ることがあると言われています。
また、「キーン」という耳鳴りが現れた場合、それは耳が限界を訴えているサインかもしれません。
しかも、難聴は一度進行すると基本的に治らないため、予防がとても大切です。
✅ポイント
-
音量は小さめを心がける(目安は50〜60%以下)
-
1時間ごとに耳を休ませる
-
耳鳴りを感じたらすぐ使用をやめよう
正しい使い方で耳を守ろう

イヤホンを安全に使うためには、正しい使い方を意識することが何より大切です。
【耳を守るイヤホンの使い方】
-
音量はできるだけ小さく(最大音量の半分以下)
-
1〜2時間に一度はイヤホンを外して耳を休める
-
耳がかゆい・痛いと感じたらすぐ使用を中止する
-
イヤホン本体を定期的に消毒・清掃する
また、運転中に使う場合は、片耳イヤホンや骨伝導イヤホンなど、耳をふさがないタイプを選ぶのも耳の健康を守るポイントです。
たとえば、骨伝導イヤホンなら耳の中に直接音を流さないので、耳の負担をかなり軽減できます。
✅まとめ
-
使い方次第で耳へのダメージを防げる
-
音量・時間・清潔管理を意識する
-
少しでも異変を感じたらすぐに使用を控えよう
運転中におすすめのイヤホンタイプとは?
イヤホンを使いたいけど、違反にならないか心配…。そんな方のために、運転中でも比較的安全に使いやすいイヤホンタイプを紹介します。それぞれの特徴を理解して、自分に合ったものを選びましょう!
耳をふさがない「骨伝導イヤホン」って?

骨伝導イヤホンとは、耳をふさがずに、骨を通して音を伝えるイヤホンのことです。
普通のイヤホンは耳の中に音を送りますが、骨伝導は頬骨や側頭部の骨を振動させて音を届けます。
【骨伝導イヤホンのメリット】
-
耳をふさがないので外の音が普通に聞こえる
-
長時間つけても耳が蒸れない
-
難聴リスクが少ないとされている
たとえば、Shokz(旧AfterShokz)OpenRunのような人気モデルは、運転中でも耳を完全に開けたまま使えるので、
サイレンやクラクションにもすぐ反応できます。
✅まとめ
-
骨伝導イヤホンは運転中に最もおすすめ
-
外部音をしっかり聞きながら通話や音楽が楽しめる
-
交通事故リスクを減らせるイヤホンタイプ
片耳対応のBluetoothイヤホン

もう一つの選択肢が、片耳対応のBluetoothイヤホンです。
文字通り、片耳だけに装着して使うタイプのイヤホンで、両手を使わずに通話ができる設計になっています。
【片耳Bluetoothイヤホンのメリット】
-
一方の耳は空いているので外の音が聞こえる
-
軽量で長時間つけても疲れにくい
-
通話専用設計のモデルも多く、クリアな音質
たとえば、ビジネスマンに人気のJabra TalkシリーズやAnker Soundcore V30iなどは、片耳用で、
運転しながら通話しやすいデザインになっています。
✅注意点
-
音楽用ではなく「通話重視」のモデルを選ぼう
-
音量を上げすぎないよう気をつけよう
-
シンプルな操作性もチェックポイント
✅まとめ
-
通話メインなら片耳Bluetoothイヤホンが便利
-
軽くて耳の負担も少ない
-
「片耳だけ使用」が安全運転の基本
カーナビ・車載マイクとの連携も検討しよう

さらに、最近の車には、カーナビや車載マイク機能を活用する方法もあります。
これならイヤホンを使わずに、ハンズフリー通話や音楽操作ができます。
【カーナビ・車載マイクのメリット】
-
イヤホン不要で周囲の音に常に注意できる
-
車内スピーカーとマイクで通話・音楽が完結
-
運転中の操作もカーナビ画面で簡単
たとえば、トヨタ、日産、ホンダなどの純正ナビにはBluetooth通話機能が標準搭載されていることが多いです。
また、後付けのハンズフリーキットも市販されています。
✅ポイント
-
新しい車ならナビ連携を最優先に検討
-
古い車でも後付けBluetoothユニットをつけられる場合あり
-
イヤホン不要なので最も安全性が高い方法
運転中でも使いやすいイヤホン10選
ここでは、運転中でも使いやすく、違反リスクを下げながら快適に使えるイヤホンを10個紹介します。すべて「耳をふさがない」「片耳使用ができる」「運転に集中できる」ことを重視して厳選しました!
1. Shokz OpenRun(骨伝導イヤホン)
おすすめポイント:
-
耳をふさがず、外音をしっかりキャッチ
-
超軽量で長時間ドライブでも疲れにくい
-
防水仕様で汗や雨にも強い
2. Shokz OpenComm(骨伝導・マイク付き)
おすすめポイント:
-
高品質マイク付きでクリアな通話が可能
-
骨伝導なので周囲の音もバッチリ聞こえる
-
専用設計でビジネス通話にも最適
3.JVCケンウッド KENWOOD KH-M500-B(片耳Bluetoothイヤホン)
おすすめポイント:
-
ノイズキャンセリングマイク搭載
-
約7時間連続通話できるロングバッテリー
-
軽くて耳に負担が少ない
4. Anker Soundcore V20i
おすすめポイント:
-
低価格で高性能、コスパ抜群
-
コンパクト設計で長時間装着も快適
-
音質もクリアで通話に最適
5. AfterShokz OpenMove(骨伝導イヤホン)
おすすめポイント:
-
手ごろな価格で骨伝導デビューにぴったり
-
6時間連続再生、短時間充電にも対応
-
シンプル設計で操作も簡単
6. Plantronics Voyager 5200(片耳Bluetoothイヤホン)
おすすめポイント:
-
風切り音も防ぐ高性能マイク
-
4つのマイクで騒音カット、車内でもクリアな通話
-
耳にぴったりフィットする設計
7. Shokz OpenFit2(オープンイヤー型イヤホン)
おすすめポイント:
-
骨伝導ではなく「耳掛け式」オープンイヤータイプ
-
周囲の音も自然に聞こえる安全設計
-
音漏れが少なく、音楽も高音質
8. JVC HA-BD10BT(骨伝導イヤホン)
おすすめポイント:
-
国内メーカー製で安心の品質
-
防水・防塵仕様でタフに使える
-
シンプル操作で運転中でも扱いやすい
9.Nakamichi ナカミチサウンド
おすすめポイント:
-
価格が安いのに通話品質は高評価
-
最大28時間連続使用可能
-
LED電量表示・片耳モードあり
10. BONX Grip(チーム通話対応オープンイヤー型)
おすすめポイント:
-
グループ通話ができる珍しい機能搭載
-
耳をふさがず自然な会話感覚
-
耳にしっかりフィットし運転中もズレにくい
運転時の安全な通話・音楽の楽しみ方
イヤホンを使うにしても、安全を守るためには正しい使い方が欠かせません。この章では、運転中に通話や音楽を楽しみながらも、周囲への注意を怠らないためのポイントを詳しく解説していきます。
音量は小さめに設定しよう

運転中にイヤホンを使う場合、音量はできるだけ小さく設定することが大切です。
大音量で音楽や通話をしていると、クラクションや緊急車両のサイレンが聞こえず、重大な事故につながる危険があります。
【音量設定の目安】
-
スマホやイヤホンの音量を50%以下にする
-
周囲の音が無理なく聞こえる程度にする
たとえば、耳元で車のエンジン音や外のざわめきが聞こえるくらいが理想です。
音楽を楽しみたい気持ちはわかりますが、運転中は「BGM感覚」で小さめに流すくらいがベストです。
✅まとめ
-
音量は「小さすぎるかな?」と思うくらいが安全
-
窓を開けたときに外の音が聞こえなければ危険
-
音楽や通話よりも、安全確認を最優先に!
外の音が聞こえることを意識する

運転中に大切なのは、目だけでなく耳からも周囲の情報をキャッチすることです。
イヤホンを使う場合でも、常に外の音が聞こえる状態を意識しましょう。
【外の音を聞くべき理由】
-
救急車や消防車のサイレンにすぐ気づける
-
後方から近づくバイクや車を察知できる
-
クラクションなど危険を知らせる音を逃さない
たとえば、道路脇で子どもたちが遊んでいる声や、踏切の警報音にすばやく反応できるかが、安全運転のカギになります。
骨伝導イヤホンや片耳イヤホンを使っていても、外音が聞こえにくいときは音量を下げる、場合によっては一時的に外すなど臨機応変に対応しましょう。
✅まとめ
-
常に外部の音が聞こえるかチェックする
-
周囲の変化に素早く気づける運転を心がけよう
-
音が聞こえないと感じたら即対応を!
安全な場所に停車して操作しよう

運転中にイヤホンの設定を変えたり、スマホを触ったりするのは非常に危険です。
どうしても操作が必要な場合は、安全な場所に停車してから行いましょう。
【安全な操作の流れ】
-
コンビニやパーキングエリアなどに寄る
-
路肩などに停車する場合も、ハザードランプを点灯
-
停車後にイヤホンの設定やスマホ操作を行う
たとえば、通話相手を変えたい、音楽をスキップしたいと思ったら、必ず車を止めてから操作します。
「ちょっとだけだから」と運転中に操作すると、前方不注意になり、わずか1秒の油断で事故を起こしてしまう可能性もあります。
✅まとめ
-
運転中の操作は絶対にNG
-
必ず安全な場所で停車してから操作する
-
少しの手間が自分と周囲の命を守る
知っておきたい!運転中の音響機器使用マナー
イヤホンや音響機器を使うときは、違反かどうかだけでなく、「周りへの配慮」もとても大切です。この章では、安全運転を守るだけでなく、周囲に不快な思いをさせないためのマナーについて解説します。
他のドライバーや歩行者への配慮

車を運転するということは、道路を使うみんなと空間を共有しているということです。
イヤホンや音響機器の使い方ひとつで、周囲に迷惑をかけたり、事故につながる可能性もあります。
【配慮すべきポイント】
-
クラクションやサイレンにすぐ反応できる状態を保つ
-
急ブレーキ・急ハンドルなど周囲を驚かせない運転を心がける
-
歩行者や自転車の動きにも十分注意する
たとえば、歩道の近くを走っているとき、子どもが飛び出してくる可能性もあります。
イヤホンで外の音が聞こえなかったら、咄嗟の反応が遅れ、大事故になるかもしれません。
✅まとめ
-
イヤホン使用中でも周囲への注意は最優先
-
ほかの車や歩行者の動きに敏感になろう
-
「自分だけ良ければいい」という運転は絶対にしない
同乗者がいるときの気遣い

同乗者がいる場合は、さらに気を配る必要があります。
自分がイヤホンを使っていると、同乗者との会話がしにくくなったり、車内の空気が悪くなったりすることがあります。
【同乗者への配慮ポイント】
-
イヤホンは基本使わず、スピーカーフォンや車載オーディオを使う
-
どうしてもイヤホンが必要なら一言断りを入れる
-
会話の途中でイヤホンに夢中にならない
たとえば、家族や友人とドライブしているのに、自分だけイヤホンで通話や音楽に集中していたら、
「なんだか無視されてるみたい」と思われても仕方ありません。
✅まとめ
-
同乗者とのコミュニケーションを大切に
-
イヤホンより「会話」を優先しよう
-
必要な場合は事前に説明しておくのがマナー
公共交通機関の規則との違いも理解しよう

公共交通機関(電車・バス)では、イヤホンや音響機器の使用マナーが厳しくルール化されています。
一方、自家用車は比較的自由ですが、だからこそ自己管理が必要です。
【公共交通機関での主なルール】
-
優先席付近ではイヤホンでも音漏れ禁止
-
携帯電話の通話はNG
-
大きな音量での音楽再生はマナー違反
運転中も、周囲に迷惑をかけないという意味では考え方は同じです。
たとえば、音漏れするような爆音でイヤホンから音を流していると、窓越しに周りのドライバーに聞こえることもあります。
そんな無神経な行動は、トラブルのもとにもなりかねません。
✅まとめ
-
公共交通機関と同様に「周りへの気配り」が必要
-
車内は自由な空間でも、周囲への配慮を忘れない
-
音響機器の使い方に責任を持とう
まとめ:イヤホンを安全に使って快適なドライブを
この記事では、運転中にイヤホンを使うことの法律・安全性・おすすめ機種などを幅広く解説してきました。最後に、もう一度ポイントを整理しながら、安全で快適なドライブを楽しむための心構えをお伝えします。
法律とマナーを守って楽しく運転

まず大前提として、イヤホンを使う場合でも道路交通法と各都道府県の規則を守ることが大切です。
また、法的にOKでも、周囲への配慮を忘れてはいけません。
【守るべきポイントまとめ】
-
両耳イヤホンは禁止されている地域が多い
-
片耳でも周囲の音が聞こえる状態をキープ
-
クラクションやサイレンにすぐ反応できることが必須
ルールを守りながら運転することが、自分自身だけでなく、周りのドライバーや歩行者を守ることにもつながります。
✅まとめ
-
「違反しなければいい」ではなく「みんなが安心できる運転」を心がけよう!
安全第一の意識が大切

イヤホンを使ったドライブは便利な面もありますが、最優先すべきは常に「安全運転」です。音楽や通話は「運転の妨げにならない範囲」で楽しむようにしましょう。
【安全運転のためにできること】
-
音量を控えめに設定する
-
運転中の操作は控える
-
疲れたら休憩を取る
たとえば、ちょっとした通話のために注意がそれてしまい、事故につながることもあります。
「ちょっとだけなら大丈夫」と思わず、常に最悪のケースを想定して慎重に行動することが大切です。
✅まとめ
-
イヤホンを使う時でも「今、自分は安全に運転できているか?」を常に意識しよう!
骨伝導や片耳イヤホンを上手に使おう

安全性を考えるなら、イヤホン選びも非常に重要です。
特におすすめなのは、骨伝導イヤホンや片耳対応のBluetoothイヤホン。
【おすすめイヤホンの特徴】
-
骨伝導イヤホン → 外音を自然に取り込みながら音楽や通話ができる
-
片耳Bluetoothイヤホン → 周囲の音をしっかり聞きながら通話ができる
たとえば、Shokz OpenRunのような骨伝導イヤホンは、運転中でもサイレンやクラクションを聞き逃さず、安全に運転できる工夫がされています。
✅まとめ
-
「耳をふさがない」「周囲の音が聞こえる」イヤホンを選ぼう
-
機器に頼るだけでなく、自分の注意力も常に高く持とう!





コメント