誰かの訃報が届いたとき、どう対応すればいいのか戸惑う方も多いのではないでしょうか。
お悔やみの言葉の伝え方や、お通夜・葬儀に参列できない場合のマナー、香典・お供え・お線香の送り方まで、正しく丁寧に対応するためには基本的な知識が必要です。
本記事では、訃報を受けたときにまずやるべきことから、返信の例文、贈り物の選び方や避けるべきNG行動までをわかりやすく解説します。突然の知らせにも落ち着いて対応できるよう、この記事を読んでしっかり備えておきましょう。
目次
訃報とは?届いたときの基本マナー
突然、身近な人が亡くなったという知らせ(訃報)が届いたら、どう対応すればよいのか戸惑うものです。この章では、訃報の意味や、連絡を受けたときにすぐ取るべき行動、家族や周囲への伝え方についてわかりやすく解説します。
訃報ってどういう意味?

「訃報(ふほう)」とは、人が亡くなったという知らせのことを指します。
身内や知り合いが亡くなったときに、その事実を周囲に伝えるために使われます。
訃報が伝えられる方法としては、以下のようなものがあります。
-
電話
-
LINEやメール
-
SNS(ただし公にしないことが望ましい場合も)
- 郵送される死亡通知や新聞のおくやみ欄
「○○さんが亡くなられたそうです」といった連絡が届いたら、それが訃報です。
📌 語源にも注目
「訃」は“死を知らせる”という意味の漢字です。「報」は“知らせる”という意味で、合わせて「死を知らせる」という言葉になります。
連絡を受けたときにまずすること

訃報を受け取ったら、まずは深呼吸をして落ち着くことが大切です。驚きや動揺があっても、慌てて行動するのではなく、次のように対応しましょう。
【訃報を受けた直後にすべきこと】
-
丁寧に話を聞く
→ 特に相手が家族や関係者の場合は、感情的にならずに静かに聞く姿勢をとります。 -
お悔やみの言葉を伝える
→ 例:「ご愁傷さまです」「心よりお悔やみ申し上げます」など。 -
通夜・葬儀の予定を確認する
→ 日時・場所・服装の案内があるかを確認します。 -
参列の可否を考える
→ 行けるかどうかの判断をし、後の対応につなげます。
📌 注意点
「なんで亡くなったの?」などと詳細をすぐに聞くのは、マナー違反になることがあります。相手の気持ちに寄り添う姿勢を持ちましょう。
家族や周囲への伝え方

訃報を受け取ったときは、自分一人で抱え込まず、必要な人に静かに伝えることも大切です。ただし、伝える相手や方法には配慮が必要です。
【誰に伝えるべき?】
-
一緒に暮らしている家族(特に親や兄弟姉妹)
-
故人と関係のあった共通の知人や親戚
-
同じ職場や学校の人(連絡役であれば)
【伝えるときのポイント】
-
声のトーンは静かに、冷静に
-
「亡くなられたそうです」「ご逝去されました」と丁寧に表現する
-
伝えたくない、または知らせるべきでない人には無理に伝えない
📝 伝え方の例文(口頭・LINE)
-
「突然のことで驚かれると思いますが、○○さんが亡くなられたそうです。お通夜は○月○日に○○で行われるそうです。」
-
「○○さんがご逝去されたと連絡がありました。詳しくは○○さんに確認してみてください。」
📌 SNSでの共有は注意
ご遺族の希望で「身内だけに知らせたい」というケースもあります。勝手にSNSに投稿するのは控えましょう。
訃報への返信・返事の正しいマナー
訃報を受け取ったとき、「返事を返すべき?」「どんな言葉を使えばいいの?」と悩む人も多いでしょう。この章では、訃報に対する返信の必要性や、LINE・メール・電話など連絡手段別のマナーと例文について、具体的に解説します。
連絡をもらったら返すべき?

基本的に、訃報の連絡をもらったらお礼やお悔やみの気持ちを伝えるのがマナーです。とくにLINEやメールなど、文章で訃報が届いた場合は、短くてもいいので返事をしましょう。
【返事が必要なケース】
-
LINE・メール・メッセージアプリなどで届いたとき
-
個人的に知らせてくれた相手に対して
【返事が不要な場合】
-
全体向けの一斉メールや社内通知
-
公的な葬儀案内状(返信してもよいが、必須ではない)
📌 返事はなるべく当日中に
訃報は急なことが多いので、できるだけ早めに返事をするのが望ましいです。24時間以内を目安にしましょう。
LINEやメールでの返事例

LINEやメールで返信する場合は、簡潔で丁寧な言葉を使うことがポイントです。絵文字や感嘆符(!)などは避けましょう。
【基本の文例】
「ご連絡ありがとうございます。突然のことで驚いています。ご家族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。」
【参列できない場合】
「このたびはご愁傷さまです。お通夜・葬儀には伺えませんが、心よりご冥福をお祈りいたします。」
【香典を送りたい場合】
「参列が難しいため、後日香典をお送りさせていただきます。ご受納ください。」
📌 NGな書き方の例
-
「びっくりしました!」
-
「なんで亡くなったんですか?」
→ 敬意や思いやりがない印象を与えるため避けましょう。
電話で伝える場合の注意点

電話で連絡を返す場合は、話し方や時間帯に気をつける必要があります。特に、相手が深く悲しんでいる可能性があるため、配慮が重要です。
【電話をかけるときのマナー】
-
時間帯は朝9時〜夜8時までが目安
-
長電話は避け、要点を静かに伝える
-
周囲が静かな場所からかける
【話し方の例】
「このたびはご愁傷さまです。突然のことで驚きました。何もできませんが、心からお悔やみ申し上げます。」
📌 避けたほうがよい言葉
-
「信じられない」「どうして…?」
→ 相手をさらに混乱させたり、傷つけてしまう可能性があります。
通夜・葬儀に行けないときの対応方法
訃報を受けたけれど、どうしても通夜や葬儀に参列できないこともあります。そんなときは、行けないことを丁寧に伝え、別の形で弔意(ちょうい:哀悼の気持ち)を示すのが大切です。この章では、欠席の伝え方と、その後の対応について解説します。
欠席しても失礼にならない配慮とは

お通夜や葬儀は、故人(亡くなった方)にお別れを伝える大切な機会ですが、どうしても都合がつかないこともあります。行けないからといって、必ずしも失礼にはなりません。
【よくある欠席理由】
-
仕事や学校の都合
-
遠方で移動が難しい
-
体調不良(感染症への配慮も含む)
-
家族の事情(介護や子育てなど)
重要なのは、「行けないこと」に対する誠実な気持ちを伝えることです。
📌 欠席連絡は早めに!
なるべく通夜や葬儀の前日までに、電話やメッセージで一報を入れておきましょう。
連絡のしかたと例文

参列できない場合は、理由を簡潔に添えつつ、心を込めたお悔やみの言葉を伝えるのがマナーです。
【電話で伝える例】
「このたびはご愁傷さまです。本来であれば伺うべきところですが、やむを得ない事情で参列できず、申し訳ありません。心よりお悔やみ申し上げます。」
【LINE・メールの例】
「突然のご訃報に、心よりお悔やみ申し上げます。ご葬儀には伺えず恐縮ですが、ご冥福をお祈りいたします。」
📌 注意ポイント
・「忙しくて行けません」はNG → 理由は曖昧か丁寧に
・行けないことへの申し訳なさをしっかり伝えるのが礼儀
後日あらためて弔意を伝えるには

参列できなかった場合、後日あいさつや贈り物を通じて弔意を示すことが可能です。これにより、故人やご遺族に対する気持ちがきちんと伝わります。
【できることの例】
-
香典を郵送する(現金書留で)
-
お線香やロウソクを送る
-
落ち着いたころに弔問(訪問)する
-
手紙やお悔やみ状を送る
【お悔やみの手紙 例文】
「このたびはご愁傷さまです。ご葬儀に伺えず、大変失礼いたしました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。」
📌 訪問のタイミングは四十九日(しじゅうくにち)以降が目安
落ち着いた頃合いを見て連絡し、「ご都合のよい時にお線香をあげさせてください」と声をかけましょう。
お通夜・葬儀に参列する場合の準備とマナー
訃報を受けてお通夜や葬儀に参列する場合は、事前の準備や当日のマナーがとても大切です。この章では、服装・香典・会場でのふるまい方について、恥ずかしくないよう基本的なマナーをわかりやすく解説します。
服装・持ち物の基本ルール

葬儀や通夜では、故人に敬意を表すための服装や持ち物のマナーが決まっています。服や靴、バッグは派手なものを避け、黒を基調にしたものを選びます。
【大人の基本スタイル】
-
黒の喪服(礼服)
-
白いシャツ(男性)
-
黒いパンプス・黒い靴下
-
飾りの少ない黒のバッグ
【学生や制服の場合】
-
学校の制服でOK(ブレザー、黒靴など)
-
派手なアクセサリーやカラーネイルは控える
📌 香典やハンカチも持参を
香典は必須ではありませんが、持参が望ましいです。ハンカチは白または黒を選びましょう。
香典の金額とマナー

香典(こうでん)とは、お悔やみの気持ちを表すために包むお金です。宗教・地域・関係性によって金額に差がありますが、一般的な目安を参考にすると安心です。
【香典の金額目安】
| 故人との関係性 | 金額の目安 |
|---|---|
| 友人・知人 | 3,000円~5,000円 |
| 親しい同僚・上司 | 5,000円~10,000円 |
| 親戚・親族 | 10,000円~30,000円 |
📌 香典のポイント
-
新札は避け、折り目のあるお札を使う(「準備していた印象」を避けるため)
-
不祝儀袋(「御香典」「御霊前」など)に包む
-
表書きは筆ペンや薄墨のサインペンで書くのが一般的
当日のふるまい方と挨拶例

お通夜や葬儀では、静かに落ち着いた行動を心がけることが何よりのマナーです。悲しみに暮れるご遺族に失礼がないよう、言葉や態度に配慮しましょう。
【当日のふるまいの基本】
-
会場では私語や笑い声を控える
-
携帯電話の電源はオフまたはマナーモード
-
焼香(しょうこう)は前の人を真似すればOK
-
写真撮影は原則NG
【ご遺族への挨拶例】
「このたびはご愁傷さまです。心よりお悔やみ申し上げます。」
📌 注意点
あまり多く話しかけたり、「どうして亡くなったの?」などの質問をするのは失礼にあたります。そっと寄り添う気持ちを大切にしましょう。
香典・供花・お供えを送る場合のマナー
通夜や葬儀に参列できない場合や、より丁寧な弔意を表したいときには、香典・供花(きょうか)・お供えを送ることがあります。ただし、宗教や地域によって考え方やマナーが異なるため、正しい方法で送ることが大切です。この章では、それぞれの基本と送り方の注意点を解説します。
香典を送るときの封筒や宛名の書き方

香典を送る際には、専用の封筒(不祝儀袋)と現金書留(げんきんかきとめ)を使うのが基本です。
【不祝儀袋の書き方と選び方】
-
表書き:「御霊前」または「御香典」が一般的
(仏教の場合は「御仏前」とすることも) -
名前:自分のフルネームを中央下に書く(連名の場合は横並び)
-
水引:白黒または銀色の結び切り(※結婚式とは違うので注意)
【現金書留での送り方】
-
郵便局で「現金書留封筒」を購入(1枚21円程度)
-
香典を中袋ごと入れ、封をする
-
送り先の住所・宛名は「〇〇家ご遺族様」または「喪主様」
📌 宛名が不明な場合は、電話で確認するか、共通の知人に相談しましょう。
供花・お供えの選び方と相場

供花(きょうか)やお供え物は、「心を込めた贈り物」として選ぶことが大切です。見た目が華やかすぎるものや、強い香りのものは避けましょう。
【供花(お花)の選び方】
-
白・紫・淡い色合いの花(菊、百合、カーネーションなど)
-
ラッピングは控えめに
-
立て札を付けるのが一般的(名前と差出人)
【お供え物の例】
| 種類 | 内容例 | 相場 |
|---|---|---|
| 線香・ロウソク | 無香タイプ、煙少なめタイプ | 2,000~5,000円 |
| お菓子 | 日持ちのする和菓子・果物 | 3,000~5,000円 |
| お茶 | 煎茶や緑茶など、香り控えめのもの | 2,000~3,000円 |
📌 宗教によっては供花を受け取らないこともあります。事前に確認するのがベストです。
送るタイミングや注意点

贈り物を送るタイミングにもマナーがあります。基本は通夜・葬儀の前日または当日の朝までに届くようにします。
【タイミングの目安】
-
供花:通夜や葬儀の前日または午前中までに届くよう手配
-
香典:通夜・葬儀当日持参 or 現金書留で後日(なるべく1週間以内)
-
お供え:四十九日までに届けばOK。タイミングに合わせて贈ると丁寧
📌 注意すべきポイント
-
相手が受け取れる状態か(外出・入院など)を確認
-
熨斗(のし)には「志」や「御供」などを使う
-
会社名や個人名を明確にして、誰からかわかるようにする
訃報時に送るお線香・ロウソクのおすすめ商品10選
通夜や葬儀に参列できないときや、後日あらためて気持ちを伝えたいときに便利なのが「お線香」や「ロウソク」のギフトです。最近では香りがやさしいタイプや、火を使わないLEDタイプなど、贈る側・受け取る側に配慮した商品が多数あります。ここでは、失礼にならず気持ちが伝わるおすすめ品を紹介します。
お彼岸 線香 贈答用 送料無料 花くらべ 3筒セット
複数の香りを楽しめる、煙の少ないタイプのお線香。
【美麗香二種香】お線香セット 煙の少ない微煙タイプ 白檀・沈香の香り
白檀と沈香の香りが楽しめ1筒に120本入っております。煙が少なく、優しい香りが定評で、リラックスした時間をお届けします。品のある包装紙で丁寧に包まれ、御供熨斗が添えられていますので、贈り物として最適です。商品は緩衝材でしっかり梱包され、安心してお手元に届きます。お届け先様にも負担がかからないよう配慮されており、心温まる贈り物として喜ばれることでしょう。
花くらべ二種香 高級桐箱入り 煙の少ない微煙タイプ
永楽屋オリジナル花くらべ2種香 金木犀・紅梅の香り。包装を解いて頂くと、高級桐箱の中に可愛らしいパッケージに思わず心が和みます。筒型の華やかなパッケージに、金木犀・紅梅の香りの二種類のお線香が入っています。 御進物に最適な高級桐箱入り 家族葬やお悔やみを後から知って準備される時や仏事の法要や喪中見舞い、お盆の贈答品としてもお使いいただけます。 仏事全般でお使いいただける「御供」の結び切り熨斗付きです。
マルエス ろうそく 花 絵 1号5 12本入り
ローソクに1月から12月までの月の花を転写しました。
毎月のお墓参り等にその月の花が転写されたローソクをお使い下さい。
絵ろうそく 花ろうそく 3号 6本 入り 手描き
新年、お盆など、50分ぐらいの丁寧に礼をする特別な時に振る舞うと素敵な時間がいただける手書き絵ローソク。揺らぎ燃え盛る炎を見ると動物は闘志が宿る。大切な人と一緒に神秘的な時間を共有する。
花のギフト社 お供え 花 線香 お供え物
故人を偲ぶ生花アレンジと日本香堂のお線香ローソクセット。清楚な白い百合を中心に菊やトルコキキョウなどのお花でアレンジ。 サイズの大きなアレンジメントですので、連名でお贈りする場合にも最適です。 言葉に出来ない「想い」をお花とお線香に託して伝えます。
進物 贈答用 櫻人 ギフト線香&ろうそく詰め合わせ 桜葉エキス配合
桜葉エキス配合で、桜の下にいるような、ほのかなさわやかな甘い香りのするお線香&ローソクのセットです。
普段使いはもちろん、お彼岸やお盆のギフトとしても、ご利用いただけます。
桜が大好きだったあの人やペットちゃんを偲び、たくさんご供養してください。
香典袋 ふくさ 薄墨筆ペン 慶弔両用
香典袋1枚(中袋付き)、ふくさ、薄墨筆ペン1本、説明書付きのセットです。
淡路梅薫堂のお線香セット お線香を送る お線香贈答用
失礼しない黒薄消しおしゃれ箱お線香ギフト。 線香 贈答 店舗。線香 ギフト 人気 天然白檀をあわせた五種類の落ち着いた花の香りお香・お線香詰め合わせ。
お香 キンモクセイ 線香 煙の少ない
キンモクセイの香りに合う最高級のインド産老山白檀など様々な成分をブレンドしています。花と香木、それぞれの個性を引き出しつつ、全体の調和を保つように配合しています。シーンで変化する「 奥行きのある金木犀の香り」があなたを心地よい空間へと誘います。
弔意を伝える例文・LINEや手紙の書き方
通夜や葬儀に参列できない場合や、あらためて気持ちを伝えたいときには、LINE・メール・手紙などで「弔意(ちょうい)」=お悔やみの気持ちを表すことが大切です。
この章では、文例を交えながら、失礼にならず心が伝わるメッセージの書き方を解説します。
行けない時に送る例文

通夜や葬儀に行けないときでも、メッセージで気持ちを伝えるだけで、ご遺族に安心感や配慮が伝わります。
以下に、状況に応じた例文をご紹介します。
【LINE・メールの文例】
このたびはご愁傷さまです。突然のことで驚いております。
ご葬儀には伺えませんが、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
ご連絡ありがとうございます。事情があり参列できず申し訳ありません。
落ち着かれましたら、改めてご挨拶させていただければと思っております。
📌 ポイント
-
短くても「ご愁傷さまです」「ご冥福をお祈りします」の表現を忘れずに
-
絵文字やスタンプ、カジュアルすぎる言葉は避けましょう
香典を郵送する場合の例文

香典を現金書留で送る際には、簡単な手紙やメッセージを添えるとより丁寧です。便せん1枚でも気持ちは伝わります。
【香典同封の手紙文例】
ご訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
ご葬儀に伺えず大変失礼いたしました。
心ばかりではございますが、香典を同封いたしますので、お納めください。
ご家族の皆さまがご無理なさらぬようお祈り申し上げます。
📌 同封の注意点
-
便せんかカードに丁寧な文字で書く(ボールペン可)
-
香典袋はのし付きで、外袋・中袋ともに記名する
-
封筒の外に「御香典在中」と赤字で記すと安心
言ってはいけない言葉に注意

弔意を伝える際には、うっかり使うと失礼になる言葉や表現があります。特に文章の場合は慎重に選びましょう。
【避けるべきNGワード】
| NG表現 | 理由 |
|---|---|
| 「ご苦労さま」 | 目上の人には失礼。葬儀では「お疲れさまでした」を使う |
| 「死んだ」「亡くなった」 | ストレートすぎる言い方。丁寧に「ご逝去されました」などに置き換え |
| 「頑張ってください」 | 悲しみに暮れている人に無理をさせる印象 |
【代わりに使いたい表現】
-
ご愁傷さまです
-
心よりお悔やみ申し上げます
-
ご冥福をお祈りいたします
-
ご逝去の報に接し、驚いております
📌 言葉だけでなく「気持ちの伝え方」が大切です。
無理に丁寧な言葉を並べるよりも、誠実さを心がけましょう。
やってはいけない訃報マナーのNG集
訃報への対応には細やかな配慮が求められます。どれだけ善意であっても、ちょっとした言葉や行動が、ご遺族を傷つけてしまうことも。
ここでは、うっかりやってしまいがちなNGマナーを具体例を挙げて紹介し、避けるべき言動をわかりやすく解説します。
相手を傷つける可能性のある言動

訃報を受け取ったとき、よかれと思って言ったことが、相手の心を逆なでしてしまうことがあります。
【避けたい言動の例】
-
「どうして亡くなったの?」と事情を根掘り葉掘り聞く
-
「まだ若かったのにね」など、余計なコメントをする
-
その場で思い出話を長々と語る
-
自分の経験談を話しすぎる(「うちの祖母のときはね…」など)
📌 大切なのは“話すより聞く姿勢”
ご遺族は深い悲しみの中にいるため、相手の気持ちを最優先に考えましょう。
うっかり使いがちなNGワード

言葉には「不幸が続く」「死を連想させる」といった意味合いを持つものがあります。葬儀や弔意の場では使わないのがマナーです。
【NGワードの具体例と理由】
| NG表現 | なぜNGか |
|---|---|
| 「重ね重ね」 | 不幸が重なることを連想させる |
| 「繰り返し」「再び」 | 縁起が悪い(不幸がまた起こると連想される) |
| 「生きているうちに会っておけば」 | ご遺族の後悔や悲しみを深くしてしまうことがある |
【代わりに使いたい表現】
-
「ご冥福をお祈りいたします」
-
「心よりお悔やみ申し上げます」
-
「ご家族の皆さまにお力添えできますように」
📌 句読点(「。」)の使い方も注意
弔辞や香典袋では、終止符(。)を避けるのが習わしです(終わりを意味するため)。
マナーにとらわれすぎない心づかい

マナーを守ることは大切ですが、一番大事なのは「相手の悲しみに寄り添う気持ち」です。形式や言葉だけが整っていても、心がこもっていなければ逆効果になることもあります。
【気持ちが伝わる行動例】
-
言葉が出てこないときは、そっと黙礼だけでも十分
-
手紙やメッセージは、きれいな文字や自分の言葉で書く
-
無理に「励ます」より、「そっと寄り添う」姿勢が◎
📌 失敗を恐れず、丁寧に気持ちを込めることが何より大切です。
宗教・地域によって違うお別れの形式
お通夜や葬儀には、仏教・神道・キリスト教などの宗教の違いや、地方ごとの風習の違いがあります。マナーを守っているつもりでも、相手の宗教や地域では非常識にあたることも。
この章では、宗教ごとの違いや香典金額の目安、迷ったときの確認方法について、わかりやすく解説します。
仏教・神道・キリスト教の違いとは
日本ではお葬式の多くが仏教形式ですが、神道やキリスト教の方もいます。宗教によってお別れの儀式や香典の表書き、ふるまい方が異なるため、注意が必要です。
【代表的な宗教ごとの違い】
| 宗教 | 特徴・儀式の内容 | 香典袋の表書き |
|---|---|---|
| 仏教 | 焼香(しょうこう)、読経、数珠を持参 | 御霊前・御香典・御仏前など |
| 神道 | 玉串奉奠(たまぐしほうてん)、拍手(音を出さない) | 御玉串料・御霊前 |
| キリスト教 | 献花、讃美歌、神父や牧師による祈り | お花料・御霊前 |
📌 数珠は仏教で使うもので、神道やキリスト教では使用しません。
地域による香典金額の目安

香典の金額は、関係性や年齢に加えて地域性も影響します。都市部と地方では相場が異なることがあるため、無理のない範囲で選びましょう。
【地域別の一般的な目安】
| 地域 | 一般的な金額(友人・知人の場合) |
|---|---|
| 東京・大阪 | 5,000円程度 |
| 東北・九州 | 3,000円~5,000円 |
| 地方全般 | 3,000円程度が主流 |
📌 親族や職場関係になると、10,000円~30,000円になることもあります。
迷ったときはどう確認する?

宗教や地域の風習が分からない場合、無理に独自の判断をせず、確認するのが一番安心です。
【確認の方法】
-
共通の知人に聞く(特に親しい人)
-
直接ご遺族に聞くのはNG(失礼になる可能性あり)
-
葬儀社や葬儀案内状に記載されていることも多い
📌 通夜・告別式の案内に「仏式」「神式」「キリスト教式」などの表記がある場合があります。それを見て対応を考えましょう。
学校・職場への訃報連絡と忌引き対応
身近な家族が亡くなった場合、学校や会社に休みの連絡をする必要があります。その際に使われるのが「忌引き(きびき)」という特別な休暇です。この章では、忌引きとは何か、何日休めるのか、そして連絡方法やマナーについてわかりやすく解説します。
忌引きとは?何日休めるの?

忌引き(きびき)とは、家族が亡くなったときに喪に服す(=しばらく静かに過ごす)ための特別な休みのことです。学校でも会社でも、事情を伝えれば認められることが多いです。
【一般的な忌引き日数の目安】
| 故人との関係 | 忌引き日数(学校・会社の例) |
|---|---|
| 両親 | 5日程度 |
| 祖父母・兄弟姉妹 | 3日程度 |
| おじ・おば・いとこなど | 1~2日程度 |
📌 日数は学校の校則や会社の就業規則によって異なるので、必ず確認しましょう。
学校や職場への連絡方法と例文

訃報で休むことになったら、早めに電話やメールで連絡するのがマナーです。特に会社やバイトの場合は、上司や担当者に直接伝えることが重要です。
【電話での伝え方(学生・社会人共通)】
「祖父が亡くなりまして、○日から○日まで忌引きをいただきたくご連絡いたしました。」
【メールの例文(社会人向け)】
件名:【忌引き休暇のご連絡】
本文:お疲れさまです。〇〇です。
祖父が逝去し、〇日より〇日まで忌引きをいただきたくご連絡いたしました。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
📌 学校の場合は保護者が連絡を入れるのが一般的です。欠席の理由は「身内に不幸がありました」と伝えるだけでOK。
忌引き中にしてはいけないこと

忌引きはあくまで「喪に服す時間」です。普段のお休みと違い、羽を伸ばして遊ぶための休暇ではありません。
【控えたほうがよい行動】
-
SNSへの投稿(旅行・外食・遊びなどの写真)
-
カラオケやテーマパークなどの娯楽施設に行く
-
友人との集まりに参加する(特に公の場)
📌 「周囲からどう見られるか」にも配慮を
たとえ形式的には問題なくても、第三者から「不謹慎」と思われる行動は避けましょう。
大切な人を失ったときの心の向き合い方
家族や友人、大切な人が亡くなったとき、心には大きな穴があいたような感覚になるものです。悲しみをどう受け止め、どう過ごしていけばいいのかは、人それぞれで正解はありません。この章では、喪失感との向き合い方や心のケア方法についてやさしくお伝えします。
悲しい気持ちは我慢しなくていい
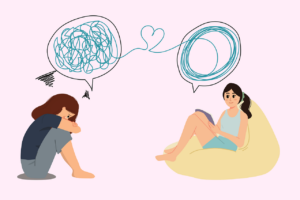
誰かが亡くなって悲しくなるのは自然な心の反応です。「泣くのは恥ずかしい」「しっかりしなきゃ」と思い込む必要はありません。
【感情を押さえ込むと…】
-
ストレスがたまりやすくなる
-
体調をくずしやすくなる
-
心の不調(無気力・不安)につながることも
📌 涙が出るのは心が回復しようとしている証拠
悲しみをきちんと感じることは、自分を大切にする第一歩です。
誰かに話すだけでも心が軽くなる

つらい気持ちを信頼できる人に話すことで、少し心が軽くなることがあります。友達や家族、先生、先輩など、誰か一人でも構いません。
【話すときのポイント】
-
無理に泣かなくていい
-
正しい言葉じゃなくてもいい
-
「聞いてくれてありがとう」だけでも十分
📌 話すことで“気持ちの整理”ができる
相手にアドバイスを求めなくても、ただ話すだけで安心感が生まれます。
時間がたっても悲しんでいい

「もう1年たったのに、まだ悲しい…」と感じても、それは全くおかしくありません。人それぞれ“心が回復するスピード”は違います。
【大切なのは自分のペースを大切にすること】
-
周りと比べなくていい
-
ふと思い出して涙が出ても大丈夫
-
自分に優しくしてあげることが大切
📌 悲しみは完全には消えなくても、ゆっくりと心の中で形を変えていきます。
✅ まとめ:喪失を乗り越えるには時間と支えが必要です
心が弱っているときは、無理をせず、頼れる人や時間に委ねましょう。悲しみと向き合うことは、大切な人との絆を大事にすることでもあります。
まとめ
訃報を受け取ると、戸惑いや悲しみでどう行動してよいか分からなくなることがあります。しかし、大切なのは「故人を想い、遺族の気持ちに寄り添うこと」です。
本記事では、訃報が届いたときにまずすべきことから、参列時のマナー、香典やお供えの送り方、弔意を伝える例文、避けるべき言動、宗教や地域による違いまで、幅広く解説しました。
対応に正解はありませんが、心のこもった行動は必ず相手に伝わります。マナーにとらわれすぎず、「丁寧に、誠実に」を心がければ、失礼にはなりません。
悲しみと向き合うことはつらいことですが、無理に前を向こうとせず、自分のペースで大切な人との時間を心に残していきましょう。





コメント